1.はじめに
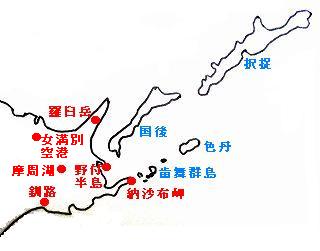
今年(2008年)9月末から
10月初めにかけて、北海道東部
のパックツアーに参加しました。
女満別空港から釧路、納沙布岬、
知床、野付半島、摩周湖などを巡
りました。
(こうして地図を眺めると、北方
四島の存在感が強く感じられます)
2.釧路
釧路で思い起こされるのは、原田康子さんの「挽歌」です。
私が高校生になった昭和30年代の初めに、ベストセラーになりました。
釧路出身の著者が、釧路を舞台にした小説です。
.jpg)
小説の内容はよく覚えていませんが、釧
路湿原や釧路川に架かる幣舞(ぬさまい)
橋などが登場していたはずです。
釧路は霧が多くて暗く寒い土地というイ
メージをもっていましたが、今回は快晴で
した。
←幣舞橋の四季の像「夏」(佐藤忠良)
↓釧路湿原の遠望
.jpg)
夜、居酒屋で牡蠣やししゃもなどを味わいました。何となく外国に出かけ
たような気分でした。
翌朝早く釧路川を散策しました。秋刀魚漁の船が停泊していました。秋刀
魚は光に寄ってくるため、電照で左舷に集まった秋刀魚を右舷に追い、右舷
に仕掛けた網で掬い揚げるのだそうです。
釧路川の幣舞橋に近い所で鮭を水揚げしていました。
.jpg) ←秋刀魚漁の船
↓鮭の水揚げ(後方に幣舞橋)
←秋刀魚漁の船
↓鮭の水揚げ(後方に幣舞橋)
.jpg) 3.納沙布岬
3.納沙布岬
釧路から納沙布岬まで走りました。
途中、厚岸を通りました。1960年(昭和35年)には、チリ沖地震によ
る津波で死者多数を含む大きな被害にあったそうです。
↓厚岸
.jpg)
風蓮湖に寄りました。
冬には白鳥が群れる湖です。
↓風蓮湖
.jpg)
納沙布岬周辺では昆布漁が盛んです。
歯舞の海は昆布が豊富ですが、ロシアの支配下に置かれているため、高い金
を払って制限時間内に収穫しなければならないようです。
昆布の良漁場である貝殻島は、僅か3キロ余り沖、目と鼻の先にあります。
.jpg) ←「返せ北方領土 納沙布岬」
↓昆布を干している海辺
←「返せ北方領土 納沙布岬」
↓昆布を干している海辺
.jpg)
根室や納沙布岬は40年近い昔に訪れたことがあります。
その当時は、「本島最東端 納沙布岬」と記された杭と、わずかな土産物屋
さんがあっただけだったような記憶があります。今は、「四島(しま)のか
けはし」という大きなモニュメント(「北方領土」返還を祈念するために作
られたシンボル像)や、北方四島交流センターなどが整備されています。
北方資料館展示室には、「北槎聞略」のコピーが展示されていました。
船頭だった大黒屋光太夫は、乗った船が漂流し、当時の首都ペテルブルグの
エカテリーナ皇帝に謁見するため、厳寒のシベリアを駆けました。「北槎聞
略」は、9年半振り(寛政4年:1792年)に帰国した大黒屋光太夫から
の聞き書きです。
.jpg) ←四島(しま)のかけはし
↓北槎聞略
←四島(しま)のかけはし
↓北槎聞略
.jpg) 4.知床
4.知床
知床を訪ねるのは初めてです。
失礼ながら、知床は地の果てというイメージを抱いていたのは正さなければ
なりません。生活状態は関西などの山間部と大差ないでしょう。
.jpg)
とは言え、現在の姿になるま
での開拓者の努力は、計り知れ
ないものがあったと思われます。
←斜里岳を背にした
じゃがいも焼酎の工場
ウトロの知床五湖の近くに、手を加えた形跡のある山林がありました。
かつて牧場として開拓され、その後放棄された場所だそうです。
.jpg) ←オシンコシンの滝
↓知床五湖のひとつ
←オシンコシンの滝
↓知床五湖のひとつ
.jpg)
オホーツク海側のウトロから根室海峡側の羅臼まで、高速縦貫道路が開通
しています。途中の峠は「知床峠」で、目の前に「羅臼岳」を仰ぎ、少し首
を振ると根室海峡を眼下にし、沖に横たわっている国後島が望めます。
.jpg)
羅臼岳は紅葉が進んでいました。
ここから国後島がはっきり見え
るのは珍しいそうです。
←知床峠から見た羅臼岳
北方領土に思いをつのらせる人にとっては、島影が見えれば一層
胸が熱くなることでしょう。
知床や国後見据え山装う てる爺
↓沖に浮かぶ国後島
.jpg)
羅臼から南下すると、野付半島があります。
エビが背を曲げたような形で突き出ている日本最大の砂嘴(さし)
で、延長28キロメートルにわたるそうです。
この半島の中央付近にネイチャーセンターがありました。
このあたりが国後島に最も接近した場所(国後島まで16キロ)
だそうです。センターに備え付けの双眼鏡で国後島を見ると、島
にある僅かな建造物が見えました。
↓野付半島から見た国後島(白いのは岩)
.jpg) 5.その他
5.その他
めったに全容を現わさないと言われる摩周湖ですが、明るい陽射しの下で
すっぱりと衣を脱いでくれました。
.jpg)
海岸沿いでは、ハマナスがあ
ちこちで実を結んでいました。
甘酸っぱいいやみのない味です
が、種が多いのが難点です。
←裏から見た摩周湖
↓熟したハマナスの実
.jpg) ↓アイヌの伝統芸能を披露してくれた人たち
↓アイヌの伝統芸能を披露してくれた人たち
.jpg) ↓小清水原生花園・濤沸湖
↓小清水原生花園・濤沸湖
.jpg) ↓冬には流氷が押し寄せるオホーツク海
↓冬には流氷が押し寄せるオホーツク海
.jpg) ↓網走付近の田園風景
↓網走付近の田園風景
.jpg) 6.おわりに
6.おわりに
日本の中では北海道が一番好きだ、と言うアメリカ人が多くいます。
広い大地が連なっている点で共鳴するからでしょう。その大地は、森林を切
り開き、野生動物を駆逐し、原住民を追いつめて開拓したものである、とい
う点でも共通しています。
.jpg)
根釧原野(こんせんげんや:
根室−釧路間の原野)を切り開
き、連なっている牧場を眺めな
がら、アメリカでの開拓史に思
いを馳せました。
←牧場の風景
北海道は広いので移動距離も半端ではありません。
今回バスでの走行距離は、4日間で合計1,200キロに達しました。
阿寒湖から網走に抜けるとき、この道路は明治時代に囚人が開いたものだ、
とガイドさんが説明してくれました。ガイドさんは北海道の暮らしのあれこ
れについても、主婦の経験を交えて語ってくれました。
バスガイドさんは、そろそろ3回目の成人式を迎えるという、美形のお嬢
さん(!)でした。年寄りには経験豊富な人が魅力です。
お別れのとき、「医者とガイドはひねているに限りますね」とお礼を言い
ました。
(散策:2008年 9月29〜10月2日)
(脱稿:2008年12月31日)
<ご参考>
・アメリカ中西部の開拓史 ⇒
オマハ
・冬の北海道旅行 ⇒
雪と光の北海道
-----------------------------------------------------------------
この記事に
感想・質問などを書く・読む ⇒⇒
掲示板
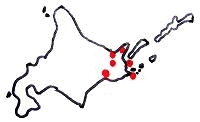
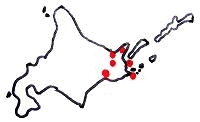
今年(2008年)9月末から 10月初めにかけて、北海道東部 のパックツアーに参加しました。 女満別空港から釧路、納沙布岬、 知床、野付半島、摩周湖などを巡 りました。 (こうして地図を眺めると、北方 四島の存在感が強く感じられます) 2.釧路 釧路で思い起こされるのは、原田康子さんの「挽歌」です。 私が高校生になった昭和30年代の初めに、ベストセラーになりました。 釧路出身の著者が、釧路を舞台にした小説です。
小説の内容はよく覚えていませんが、釧 路湿原や釧路川に架かる幣舞(ぬさまい) 橋などが登場していたはずです。 釧路は霧が多くて暗く寒い土地というイ メージをもっていましたが、今回は快晴で した。 ←幣舞橋の四季の像「夏」(佐藤忠良) ↓釧路湿原の遠望
夜、居酒屋で牡蠣やししゃもなどを味わいました。何となく外国に出かけ たような気分でした。 翌朝早く釧路川を散策しました。秋刀魚漁の船が停泊していました。秋刀 魚は光に寄ってくるため、電照で左舷に集まった秋刀魚を右舷に追い、右舷 に仕掛けた網で掬い揚げるのだそうです。 釧路川の幣舞橋に近い所で鮭を水揚げしていました。
←秋刀魚漁の船 ↓鮭の水揚げ(後方に幣舞橋)
3.納沙布岬 釧路から納沙布岬まで走りました。 途中、厚岸を通りました。1960年(昭和35年)には、チリ沖地震によ る津波で死者多数を含む大きな被害にあったそうです。 ↓厚岸
風蓮湖に寄りました。 冬には白鳥が群れる湖です。 ↓風蓮湖
納沙布岬周辺では昆布漁が盛んです。 歯舞の海は昆布が豊富ですが、ロシアの支配下に置かれているため、高い金 を払って制限時間内に収穫しなければならないようです。 昆布の良漁場である貝殻島は、僅か3キロ余り沖、目と鼻の先にあります。
←「返せ北方領土 納沙布岬」 ↓昆布を干している海辺
根室や納沙布岬は40年近い昔に訪れたことがあります。 その当時は、「本島最東端 納沙布岬」と記された杭と、わずかな土産物屋 さんがあっただけだったような記憶があります。今は、「四島(しま)のか けはし」という大きなモニュメント(「北方領土」返還を祈念するために作 られたシンボル像)や、北方四島交流センターなどが整備されています。 北方資料館展示室には、「北槎聞略」のコピーが展示されていました。 船頭だった大黒屋光太夫は、乗った船が漂流し、当時の首都ペテルブルグの エカテリーナ皇帝に謁見するため、厳寒のシベリアを駆けました。「北槎聞 略」は、9年半振り(寛政4年:1792年)に帰国した大黒屋光太夫から の聞き書きです。
←四島(しま)のかけはし ↓北槎聞略
4.知床 知床を訪ねるのは初めてです。 失礼ながら、知床は地の果てというイメージを抱いていたのは正さなければ なりません。生活状態は関西などの山間部と大差ないでしょう。
とは言え、現在の姿になるま での開拓者の努力は、計り知れ ないものがあったと思われます。 ←斜里岳を背にした じゃがいも焼酎の工場 ウトロの知床五湖の近くに、手を加えた形跡のある山林がありました。 かつて牧場として開拓され、その後放棄された場所だそうです。
←オシンコシンの滝 ↓知床五湖のひとつ
オホーツク海側のウトロから根室海峡側の羅臼まで、高速縦貫道路が開通 しています。途中の峠は「知床峠」で、目の前に「羅臼岳」を仰ぎ、少し首 を振ると根室海峡を眼下にし、沖に横たわっている国後島が望めます。
羅臼岳は紅葉が進んでいました。 ここから国後島がはっきり見え るのは珍しいそうです。 ←知床峠から見た羅臼岳 北方領土に思いをつのらせる人にとっては、島影が見えれば一層 胸が熱くなることでしょう。 知床や国後見据え山装う てる爺 ↓沖に浮かぶ国後島
羅臼から南下すると、野付半島があります。 エビが背を曲げたような形で突き出ている日本最大の砂嘴(さし) で、延長28キロメートルにわたるそうです。 この半島の中央付近にネイチャーセンターがありました。 このあたりが国後島に最も接近した場所(国後島まで16キロ) だそうです。センターに備え付けの双眼鏡で国後島を見ると、島 にある僅かな建造物が見えました。 ↓野付半島から見た国後島(白いのは岩)
5.その他 めったに全容を現わさないと言われる摩周湖ですが、明るい陽射しの下で すっぱりと衣を脱いでくれました。
海岸沿いでは、ハマナスがあ ちこちで実を結んでいました。 甘酸っぱいいやみのない味です が、種が多いのが難点です。 ←裏から見た摩周湖 ↓熟したハマナスの実
↓アイヌの伝統芸能を披露してくれた人たち
↓小清水原生花園・濤沸湖
↓冬には流氷が押し寄せるオホーツク海
↓網走付近の田園風景
6.おわりに 日本の中では北海道が一番好きだ、と言うアメリカ人が多くいます。 広い大地が連なっている点で共鳴するからでしょう。その大地は、森林を切 り開き、野生動物を駆逐し、原住民を追いつめて開拓したものである、とい う点でも共通しています。
根釧原野(こんせんげんや: 根室−釧路間の原野)を切り開 き、連なっている牧場を眺めな がら、アメリカでの開拓史に思 いを馳せました。 ←牧場の風景 北海道は広いので移動距離も半端ではありません。 今回バスでの走行距離は、4日間で合計1,200キロに達しました。 阿寒湖から網走に抜けるとき、この道路は明治時代に囚人が開いたものだ、 とガイドさんが説明してくれました。ガイドさんは北海道の暮らしのあれこ れについても、主婦の経験を交えて語ってくれました。 バスガイドさんは、そろそろ3回目の成人式を迎えるという、美形のお嬢 さん(!)でした。年寄りには経験豊富な人が魅力です。 お別れのとき、「医者とガイドはひねているに限りますね」とお礼を言い ました。 (散策:2008年 9月29〜10月2日) (脱稿:2008年12月31日) <ご参考> ・アメリカ中西部の開拓史 ⇒ オマハ ・冬の北海道旅行 ⇒ 雪と光の北海道 -----------------------------------------------------------------
この記事に感想・質問などを書く・読む ⇒⇒ 掲示板この稿のトップへ エッセイメニューへ トップページへ